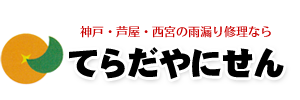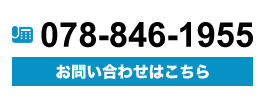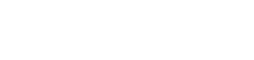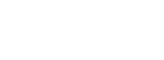こんにちは。
雨漏りと闘う男!炎の雨漏りファイターです。
今回は
『阪神地域は要注意!屋根は飛び、外壁は落下する?』
ちょっとドキッとするような内容のお話しになります。
1995年阪神・淡路大震災が起こった大変な時期、
私は建材商社の営業マンとして、神戸で震災復興に
必要な建築資材を材木店さんを通して工務店さんに
供給する仕事をしていました。
その時に見て、聞いて、経験したお話しになります。
[潜在的な不具合あるの建物]
阪神地域は阪神・淡路大震災から30年が過ぎ、
不具合が発生する可能性のある屋根材や外壁工法を
使用した年代と震災で着工数が増えた時期がかさなります。
復興が始まった1995年から2008年頃までに
建て替えられたり、損壊し修理された一部の建物には
潜在的な不具合が発生している可能性があると思われます。
その不具合発生の可能性がある住宅がなぜ増えたのか?
*震災当時の建物被害に対する風評
*阪神地域の新設住宅着工数の急増
*ノンアスベスト(無石綿)建材への移行期
*外壁下地合板への直貼り工法
*JIS規格改正前の12ミリ材の使用
順を追ってその根拠を説明させていただきます。
[震災当時の建物被害に対する風評]
2×4工法の家は倒壊せず、在来工法の家は被害が甚大
→ 外壁下地に面材、合板を張る工法が強い家になる?
和瓦の家は重みで倒壊
→屋根を軽くしないといけない、軽量のスレート瓦が最適?
という偏った情報がテレビなどのマスコミから流れました。
「倒壊した在来工法の木造住宅は古く、2×4工法の住宅は
歴史的にも築浅な建物が多かっただけのことだ」と
当時の私は思っていましたし、在来工法がダメだとういう
考えはありませんでした。
「それでは何がダメだったか?」と言えば、
復興の建て替え時に、在来工法に対しても
2×4工法と同じように下地に面材を貼って、
外壁にサイディングを直貼りしたことが

後の潜在的な不具合を起こしているという事実です。
この直貼り工法については後述させていただきます。
[神戸市内の新設住宅着工戸数の急増]
1995年 47,218戸 木造 12,800戸
2000年 13,472戸 木造 4,167戸
2024年 7,401戸 木造 3,034戸
(現在と震災直後の着工数比較 約6.4倍 木造 4.2倍)
新築建て替えと損壊した建物修理の急増による
建築に携わる職人不足で素人のにわか職人さんや、
高齢で引退した親方の現場復帰でまかなわれた。
一部の住宅には標準施工が行われず、マニュアルを
無視した工事が行われた事実があります。
建物不具合(雨漏りを含む)原因の3分類
*施工上の問題 マニュアルに準ずる標準施工が行われていない
*耐久性の問題 防水材や仕上げ材の耐久性不足
*設計上の問題 意匠性やコストを重視した無理な設計
[ノンアスベスト(無石綿)建材への移行期]
『屋根が飛ぶ→屋根材の不具合(耐久性の問題)』
健康被害問題でアスベスト使用の段階的に禁止になる事を
見すえて無石綿建材への代替屋根材が開発されました。
1975年 石綿含有率が重量の5%未満許容
1995年 石綿含有率が重量の1%未満許容
2006年 アスベスト製品全面禁止
震災復興時期のスレート瓦は石綿の含有量が
小さくそれに伴い耐久性が無い屋根材が存在した?
2006年のアスベスト製品の全面禁止を控え
ノンアスベスト(無石綿)商品への移行期になり、
その代替商品が強度不足や、層間剝離という
思いがけない不具合を発生させる要因になりました。
*パミール 1996~2008年販売
基材の層間剝離+釘頭の錆の発生

*コロニアルNEO 2001年~2008年販売
強度不足によるひび割れの発生

[外壁下地合板への直貼り工法]
外壁が落下する→外壁サイディングの施工方法で
起こる不具合(施工上の問題)
メカニズム的な見地で説明すれば、
サイディングの継ぎ手やシーリング材の
剥離部分から浸入した雨水はサイディングの
裏面に沿って流れ落ちます。
通気工法が採用された建物であれば、
通気層の中を流下して土台水切りから
外部に正常に排出されるメカニズムが働きます。
「通気工法が無い下地合板への直貼り」
この工法の場合は浸入した雨水が防水シートと
サイディングの裏面に雨水が滞留します。
滞留した雨水がサイディング基材や防水シートへ
浸透し、一次防水材や二次防水材の劣化を早め、
防水機能が失われ、下地合板、柱などの構造体に
腐食などの不具合が発生し、サイディングの
留め付け釘の強度が弱くなります。
最悪の場合は保持機能が無くなり落下します。
また下地合板が無く柱・間柱への直貼りは、
浸入した雨水が防水シートの不具合箇所から、
直接構造体内部へ浸透し、雨漏りを発生させる
可能性があります。
[JIS規格改正前の12ミリ材の使用]
サイディング厚み12㎜(耐久性の問題)
2008年 2月 JIS規格の改正
サイディングの厚みが12㎜から14㎜に変更
2008年までのサイディングは厚み12㎜が主流でした。

下地材への直貼り工法を採用した場合、
14㎜厚に比べて反りが発生する可能性が高く、
継ぎ目からの雨水浸入が下地材の腐食や
サイディング基材を劣化させることがあります。
屋根材が飛ぶ、外壁材が落下する事象
2018年 台風21号 徳島県から神戸市に上陸
最大瞬間風速 関西空港 58.1m 神戸空港 45.3m
関西空港連絡橋にタンカーが衝突
西宮市甲子園浜や神戸市六甲アイランドで高潮被害、
港の多くのコンテナが海に流された年をご記憶が
ある方もいらっしゃると思います。

あの年には実際に、屋根材が飛び、外壁が落下した
事実があります。
幸いにも2019年以降大きな被害をもたらすような
台風は来ていませんが、また、あの時と同じような
「非常に強い台風」が阪神地域に上陸した場合、
潜在的な不具合が発生している住宅は屋根材が飛び、
外壁が落下する可能性がありますのでお気を付けください。
『まとめ』
*1995年~2008年、阪神間に建てられた住宅
*通気工法が採用されていない外壁
*屋根はノンアスベスト移行期のスレート瓦
*外壁は厚み12ミリのサイディング
該当する建物でメンテナンスされていない住宅は、
非常に強い台風が来た場合、屋根材・外壁材が
飛散落下する可能性がありますので、
早急なメンテナンスの実施が必要と思われます。
『塗装工事業者の皆様へ』
塗装業者さんは見積り現調時に確認する要点
*建物建築時期
*屋根・外壁の使用材の名称・アスベスト含有確認
*外壁材の留め付け工法、通気工法の有無
上記不具合が発生している可能性がある
仕上げ材や工法を採用していれば、
再塗装では無く、貼り替えやカバー工法を
選択提案することもプロの必要なアドバイスであると
考えます。
『中古住宅の購入をお考えの皆様へ』
中古住宅の購入を考えている人も同様に
建築年数、屋根外壁の使用材料、建築工法は
仲介業者に確認して購入するべきと考えます。
1995年以降2008年までに
阪神間に建てられた住宅は特に要注意ですので、
購入する前に住宅診断(インスペクション)を
実施することも合わせてお考えください。
阪神地域に居住されている方で、震災後に建て替えられた
住宅にお住いの皆さまには、少し不安な気持ちにさせる
お話しになったかもしれません。
しかし外壁・屋根の点検、メンテナンスは重要ですので、
自宅に気になる不安な点があれば、遠慮なくご相談ください。
それでは本日のお話しはここまでとさせていただきます。