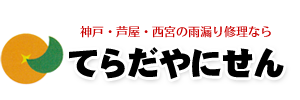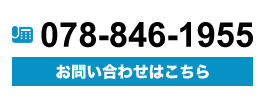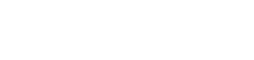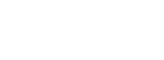こんにちは。
雨漏りと闘う男!炎の雨漏りファイターです。
今回は
「雨漏り!応急処置方法 。」
についてお話しさせていただきます。
【内 容】
応急処置の考え方とそれに基づいた方法
- 浸入水を受け止める
- 浸入口を止水する
大きく分けてこの二つの方法があります。
どちらがあなたにとって最良な方法か?
私は「浸入水を受け止める」考え方がシンプルで
取り敢えず雨漏りの応急処置方法として
ベターであると考えています。
その理由をお話しさせていただきます。
雨の頻度の高いのは3月から10月頃まで。
この時期、雨漏りでお困りの方が多くなります。
雨漏りのご相談件数も増え、積み重なっていきます。
すぐに訪問出来ても修理着手までに時間を要します。
しかし、その間にも雨降りは待ってくれず、
雨漏りは無情にも続きます。
雨漏りのポタポタはかなりのストレスになります。
そこで
取り急ぎの「応急処置」
1.浸入水を受け止める
この考え方を基に、応急処置方法をご紹介します。
[天井の雨漏り①]
【洗面器で受ける】

昔ながらの、まんがにも登場する洗面器で受ける。
この方法は落ちてくる雨水を受け止めるだけなので、
シンプルな方法ですが、天井から落ちてくる雨水が
洗面器に跳ねて、あちこちに飛び散るのでご注意!
飛び跳ねを防ぐ方法は、落下距離を短くする。
状況的に可能であれば、天井内に洗面器を設置し、
跳ねよけのタオル又は給水マットを入れておけば、
洗面器が満水になるまでは急場をしのげます。
但し、壁際に沿って流れ落ちる雨漏りには不向きです。
[天井の雨漏り②]
【マスカーで誘導する】

室内の作業養生に使用する「マスカー」という商品があります。
テープ付きの「マスカー」があり、固定するのに便利です。
まずは「マスカー」と「バケツ」をご用意ください。
「マスカー」はホームセンターで購入可能です。

天井の落水部分を中心に囲むように天井に貼り付けます。
床方向に巻き込みに浸入した雨水をバケツに誘導します。
この時、巻き込み、絞り過ぎにご注意!ください。

天井下のマスカーの空間に雨水が溜まらないように
浸入した雨水が流れ落ちる隙間を作ってください。
マスカー幅は天井高を考えて260cmは必要です。
マスカーを外す際は慎重に丁寧に剥がします。
雨水で窓枠や天井材がふやけていることがあり、
表面シートがテープと一緒に付いてきますので、
仕上げ材の剥離にはくれぐれもご注意!ください。
[サッシ枠からの雨漏り①]
【ビニールホースで誘導する】

ホース内の液体状況が一目でわかる透明ビニールホース。
窓サッシの上枠の固定ビスからの雨漏りの場合
先ず、ビスを抜けない程度までゆるめて、外に巻きだします。

ゆるめたビス先に端部を割いたホースの空洞に入れます。
ホースとサッシ上枠の接地面をビニールテープで固定し、
雨水がこぼれ出さないように取付けします。

サッシ枠上部内に滞留した雨水がビス穴から、
ホース内に移動し、内面に沿って流れ落ちます。
ホースの下部先端をバケツ内に入れ雨水を
受け止め溜めます。
さすがにバケツがいっぱいになる雨漏りはまれなので、
これで一時しのぎは可能なはずです。
但し、ビニールホースの取り付けている間は、
扉の開け閉めが出来ませんので、ご注意ください。
[サッシ枠からの雨漏り②]
【マスカーで誘導する】

マスカーを窓下枠に貼り付け、左右に30cmほど
立ち上げ、左右をサッシ横枠に沿って巻き上げ、
逆三角形の形にし、端部をバケツの中へ入れ、
ポタポタ落ちる雨水を誘導し集めます。
上部からポタポタと落ちてくる雨水が跳ね返る場合、

窓下枠にタオル又は給水マットを敷いて周囲に
飛び跳ねるのを防いでください。
これが「導水」という考え方で
浸入した雨水を拡散させず、特定の経路に
導き処理する方法です。
根本的な雨漏り「原因」を解消する方法では
ありませんが、雨水が内壁、床へ拡散、
雨溜まりを一時的に防ぐことはできます。
天井へのテープ貼り付けの際は、椅子、脚立等を利
用することになると思いますので、踏み外し転倒など
お怪我なされないようお気を付け!ください。
2.浸入口を止水する
[ベランダが原因の雨漏り]
【ブルーシートで覆う】

1階お部屋の雨漏りで、真上の2階がベランダの場合、
ベランダ内、又はベランダに接する外壁に雨水浸入口が
あると考えられます。
ホームセンターにある「ブルーシート」と「ビニールひも」を
ご用意ください。


ベランダ床の防水層を守る意味で立ち上がっている
両サイドの手摺り壁上部の手摺、または樋の支持金物に
ビニールひもでブルーシートを結び固定します。

ベランダ内部をブルーシートで包み隠すように覆って、
雨水がベランダ内に入り込まないように防ぐ方法。
この時にブルーシートの平たい部分に雨水が溜まり、
重みで破損することを防ぐために、ビニールひもで
固定する時に、少し外側に流れ落ちるように勾配を
付けることがポイントです。
[屋根が原因の雨漏り]
2階建てで2階の部屋の壁際から遠い天井に発生する
雨漏りは屋根からの雨水浸入の可能性が高く、緊急を
要する雨漏り処置の方法としてベランダと同じように
ブルーシートで覆い隠せば、屋根に雨水が
流れこまず、雨漏りを防ぐことはできます。
地震で瓦がズレた時や、台風時の強風、突風で瓦が
飛んだ時などに屋根全体をブルーシートで覆い、土嚢袋で
押さえた映像をテレビ中継などで目にする方法です。
しかし、この大掛かりな方法は使用するブルーシートの質も
大きさも違いますので、屋根屋さんや建築業者さんなど、
業界のプロの方たちが多人数で行う作業になります。
この作業は一人で出来る応急処置ではなく、素人の方が
数名で見様見真似で作業しても、うまくいくはずもなく、
落下事故、大怪我につながりますので、危険を伴うこの
応急処置作業はプロに任せて、個人ではおやめください。
[外壁のひび割れ(クラック)が原因の雨漏り]
【防水材でふさぐ】
「シーリング材」と合わせて「マスキングテープ」,
「コーキングガン」「押さえヘラ」をご用意ください。

サッシ枠周辺に接する外壁にひび割れや大きなクラックが
ある場合には雨水の浸入口になりますので、シーリング材で
ふさぐのも一時的な応急処置の方法です。

この作業をする場合は、外壁面の埃を拭き取り、ひび割れの
両際に沿って、マスキングテープを貼り、シーリング材を
打ち込み、ヘラで押さえ仕上げます。

但し、プロはシーリング材打ち込み前に、密着するように
プライマーを塗布しますが、一時的な応急処置の場合で、
その後、プロ業者さんが雨漏り修理をする場合に限り、
その工程を省く場合もあります。

1階の雨漏りは2階の外壁のサッシ周辺のクラックから
浸入することが多く、ベランダ内のひび割れ以外は
梯子作業になりますので、落下事故、大怪我をする
可能性がありますので、プロにお任せしましょう。
これが「防水」という考え方で
建物外皮に防水材料を用い雨水の浸入を防ぐ方法です。
防水材が防水機能を維持している間は防ぐことはできます。
この方法も根本的な雨漏り「原因」を解消する方法では
ありませんが、一時的に雨漏りを止めることが出来ます。
【まとめ】
建築業者でない個人の方が雨漏りの応急処置をする場合は
- 浸入水を受け止める
- 浸入口を止水する
二つの考え方による応急処置方法をご紹介しました。
どちらがあなたにとってお勧めの方法か?と言えば
「浸入水を受け止める」という考え方に基づき、
「洗面器」「マスカー」「ビニールホース」などを使用し、
雨水を誘導し溜めるという応急処置方法をお勧めします。
安全性、作業時間、費用面で有益であると考えます。
但し、ご紹介してきた各種の応急処置方法は
後にプロ業者さんが雨漏り修理をするまでの応急処置で
あり、一時的な雨漏り回避方法であるとご理解ください。
*3月下旬から4月に掛けて降る雨天期間の
「菜種梅雨(なたねつゆ)」。
*6月には旬を迎える梅の熟す時期の雨と
呼ばれる「梅雨(つゆ)」。
*積乱雲が発生しやすい夏の時期に局地的に
1時間ほどの激しい雨をもたらす「ゲリラ豪雨」。
*夏から秋にかけて、太平洋高気圧が弱まると
偏西風に乗って日本にやってくる「台風」。
この時期に集中する雨漏りのお問い合わせ。
調査作業着手から雨漏り原因の特定、修理工事まで
少しお時間をいただく場合もあります。
一件ごと丁寧に対応させていただきますので、
少しの間、「応急処置」にて雨漏り対応して
いただければという思いのお話しでした。
雨漏りは「経験」「知識」「技術」のある
雨漏りと闘う男・炎の雨漏りファイターへ
ご安心してご相談・お任せくださいませ!
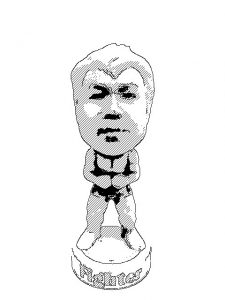
『雨漏りと闘う男!炎の雨漏りファイター』頑張ります!